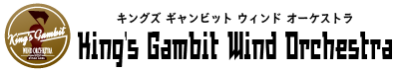第8回定期演奏会 曲紹介
目次
- アルメニアン・ダンス パート1 / A・リード
- パガニーニの主題による幻想変奏曲 / J・バーンズ
- Audivi Media Nocte / O・ヴェースピ
- 交響曲第3番「コミタスに捧ぐ」/ A・コミタス
アルメニアン・ダンス パート1 / A・リード
文:木村 颯 《当団トロンボーン奏者》
昨年生誕100周年を迎えたアメリカの作曲家、アルフレッド・リード(1921-2005)。吹奏楽を中心に多くの作品を残し、戦後のコンサートバンド文化を牽引してきた人物だ。リードの作品にはアマチュアのバンドや教育現場で演奏されることを想定されたものも多いが、奏者の技術や音楽性に制約があるなかでもそれなりの演奏に聴こえるような彼のスコアリングは、バンドの特性を熟知したリードならではの職人技である。
そんなリードの代表作ともいえるのが、この〈アルメニアン・ダンス〉パート1である。アルメニアにルーツを持つアメリカのバンドディレクター、ハリー・ベギアンの委嘱により書かれたこの楽曲は、もともと4楽章構成の組曲として構想されており、後に第2~4楽章にあたる「パート2」が出版された。各楽章間に有機的なつながりは無く、またパート1単体で起承転結がはっきりした構成になっているため、今回の演奏会のように現在ではもっぱらパート1だけで演奏されることが多い。
曲の構成は、コミタスというアルメニアの音楽家が残した5つの民謡や童謡のメドレーとなっている。一曲目の〈あんずの木〉の原曲は、コミタスがいくつかの民謡の旋律を一つの歌曲としてまとめたものであり、嘆きの心情をあんずの木に仮託した内容となっている。これをリードは大胆にも金管楽器による華やかなファンファーレにアレンジするが、一方で「こぶし」のような三連符の対旋律を伴う木管楽器による陰影に富む旋律が続きそのコントラストに引き込まれる。二曲目の〈やまうずら〉はアルメニアの有名な詩人ホヴァネス・トゥマニャンの詩にコミタスが曲を付けた童謡であり、よちよち歩くやまうずらの雛がテーマとなっている。童謡でもたびたび用いられる交唱という手法を用いることにより、リードはこの曲が持つ素朴な情景を表現する。三曲目の〈ホイ、ナザン〉の原曲は恋人への思いを歌った4分の12拍子の舞曲である。リードはこれを2+3と3+2を組み合わせた変則的な5拍子にアレンジし、この独特の変拍子の上で旋律は弾んだりベタっとなったりと多彩な表情を見せる。四曲目の〈アラギャズ〉はアルメニア国内の最高峰であるアラギャズという山の情景を歌ったものである。雄大で牧歌的な旋律からはアルメニアの大自然を感じることができるだろう。五曲目の〈行け、行け〉はアップテンポの舞曲であり、タイトルの通り駆り立てられる印象の楽曲である。リードのアレンジもダイナミクスの変化でメリハリをつけながらクライマックスまで一気に駆け抜ける。
普段の生活ではあまり触れることのないアルメニア民謡という素材を味わいながら、リードのアレンジャーとしての才能に驚嘆する、そんな一曲である。
パガニーニの主題による幻想変奏曲 / J・バーンズ
文:真柄 靖行 《当団ユーフォニアム奏者》
「パガニーニの主題による幻想変奏曲」は、アメリカの作曲家:ジェームズ・チャールズ・バーンズ(James Charles Barnes) により1988年に作曲された。曲名にあるパガニーニとは、18~19世紀のイタリアのヴァイオリニスト/作曲家ニコロ・パガニーニのことを指し、彼がヴァイオリン独奏のために作曲した『24の奇想曲』の第24番「主題と変奏」の旋律を主題とする変奏曲として書かれている。実はこの主題を用いた変奏曲は過去より様々な作曲家によって作曲されており、有名な作曲家としてはリストやブラームスやラフマニノフなどが挙げられる。
この曲の特徴はなんといっても各楽器によるアンサンブルが連なっていることだ。冒頭、中間部、最後にはTutti部分もあり、聴きなれたメロディーを非常に壮大に演出している音楽ではあるが、基本は各楽器に合わせたヴァリエーションが最大の見どころだろう。そこには、ダブルリード(オーボエやファゴット)や低音楽器など、普段単独では聞き慣れない楽器もフィーチャーされている。吹奏楽を知らない方でも、この1曲を聴けば多くの楽器の響きに触れることができる。是非各楽器の音色に注目して聴いていただきたい。
Audivi Media Nocte / O・ヴェースピ
文:真柄 靖行 《当団ユーフォニアム奏者》
Audivi Media Nocte(アウディヴィ・メディア・ノクテ)は、スイスのチューリッヒ生まれの作曲家:オリヴァー・ヴェースピ(Oliver Waespi)によって、2011年に開催された“ヨーロピアン・ブラスバンド選手権2011”の選手権部門指定課題として作曲された。なお、ここでいうブラスバンドとは、吹奏楽のことではなく、金管楽器と打楽器で構成される金管バンドを指す。その後自身にて吹奏楽編成にアレンジしたものを本日演奏する。日本では、2017年に精華女子高等学校が全日本吹奏楽コンクール全国大会で演奏し、金賞を受賞。一大センセーショナルを巻き起こした。
曲名の「アウディヴィ・メディア・ノクテ」とは、ラテン語で「我は聴きぬ、真夜中に」という意味であり、それは16 世紀イングランドの作曲家トーマス・ダリス (1505? ~ 1585) のコラール・モテットのタイトルが引用されている。モテットとは、13世紀初頭に成立したポリフォニー(多声)様式による宗教的声楽曲を指し、その後もそれぞれの時代の音楽形式の変遷に従って多様に変化し続けてきた。その中で16世紀のモテットというといくつかの学派に分かれるが世俗性は完全に排除され、より宗教音楽という色が強かった。
さて、曲の構成に話を戻そう。冒頭からエネルギッシュで華やかなファンファーレと細かな連符が共存するワクワクドキドキな前半部、ダリスのモテットにインスパイアーされた様々な楽器がエコーのようにフレーズを重ね合わせる中間部①、その後今までと一気に雰囲気が変わってファンクとジャズが現れる異色の中間部②、最後にさらにパワーアップされた冒頭のフレーズに戻り、紆余曲折あるも最後はきっちり重厚なハーモニーで締めくくられる。一度聴いたら病みつきとなり、約20分と長編曲ではあるが、飽きのこない構成となっている。
その中でやはり一番注目すべきは、中間部②で表現されるチームA:トロンボーン、チューバ、パーカッションと、チームB:トランペット、ユーフォニアム、パーカッションの2つの超絶技巧トリオアンサンブルだろう。チームAではFunkを表現した変拍子を、チームBではJazzを表現した細かい連符が見せ場であり、演奏する側も聴く側も手に汗握ることだろう。余談だが、作曲者はスコアにてソリストの立ち位置を含むセッティングの例を提示しており、そこから作曲者がこの曲に対して聴覚的だけでなく視覚的なこだわりも持っていることがわかる。
最後に、もし本演奏を聴いてこのAudivi Media Nocte に興味を持っていただけたのであれば、是非You○ubeにて原曲のブラスバンド版を聴くことをお薦めする。2012年のヨーロピアン・ブラスバンド選手権での演奏で、オランダの「ブラスバンド・スホーンホーフェン」による名演だ。ソロでの個人技やTuttiのハーモニーが素晴らしいことはもちろん、曲の終わりのスタンディング・オベーションも超必見。一度でいいのであそこまでの喝采を浴びてみたいと思うほどである。
交響曲第3番「コミタスに捧ぐ」/ A・コミタス
文:木村 颯 《当団トロンボーン奏者》
アレクサンダー・コミタス(Alexander Comitas 1957-)はオランダの作曲家。オーケストラ、合唱、吹奏楽、ファンファーレバンドなど多彩な編成の作品を手掛け、オペラ、バレエ、歌曲、交響曲、コンテストピースなど幅広いジャンルで高い評価を受ける作品を残している。本名はエデュアルド・デ・ブールといい、アレクサンダー・コミタスはペンネームである(以下デ・ブールと呼ぶ)。ポスト・モダンが席巻する時代に作曲を学んだデ・ブールは、反動的に古典的な作風に傾倒するようになった。同時に民謡にも興味を持ち世界中の民謡を調査するなかで、彼はアルメニアの民謡を数多く残したコミタス(Komitas 1869-1935)と出会う(コミタスについては当団ホームページ上の記事「アルメニアン・コラム パートⅤ」を参照)。コミタスの残したアルメニア音楽に魅了されたデ・ブールは、以来アレクサンダー・コミタスというペンネームを使うようになった。ペンネームのスペルは “Comitas” となっているが、これはラテン語で「礼儀正しさ」や「優しさ」を意味する単語であり、コミタスKomitasとのダブルミーニングとなっている。なお「アレクサンダー」はデ・ブールが敬愛するオランダのピアニスト、サス・エルネスト・アレクサンダー・ブンゲ(1924-1980)へのオマージュである。
デ・ブールのキャリアを決定づけた偉大な先人コミタス。その彼に対する賛辞を献呈するという発想を温めていたデ・ブールであったが、その想いはオランダ舞台芸術基金とオランダ王立海兵隊バンドの協力により演奏時間約60分の大規模なシンフォニーとして結実した。それがこの交響曲第三番「コミタスに捧ぐ」である。デ・ブールはこの曲を作曲した後、もうその役目は終えたとして「アレクサンダー・コミタス」というペンネームを用いるのを止めた。まさしくアレクサンダー・コミタスという作曲家の集大成となる作品なのである。
楽曲は4つの楽章により構成され、第一楽章と第二楽章の間以外はすべてアタッカで(切れ目なく)演奏される。コミタスの生涯とアルメニア人虐殺をテーマにコミタスに献呈することを意図された標題音楽でありながら、古典派の交響曲の形式を踏襲した堅牢な楽曲構成となっている。各楽章の主題にはコミタスが採集した民謡やトルコの民謡、そしてデ・ブール自身の作品から引用した旋律が用いられており、これらの主題が緻密なテクスチャを描きながら展開される。
第一楽章 「追憶」 Lento – Allegretto 変ロ短調
デ・ブールは、1935年10月パリ郊外のヴィルジュイフにある病院で死の淵にいるコミタスを想像する。アルメニア人虐殺をかろうじて生き延びるも、PTSDを発症し再起することが叶わなかったコミタスは、深い悲しみとともに自らの人生を振り返る。
短い序奏を伴うソナタ形式。序奏では全曲の中心となる主題がいくつか登場する。まずはトロンボーンにより奏でられる「私の心はすり減っている」と歌う嘆きの歌〈私は燃えている〉。それを受けるクラリネットの旋律はデ・ブールの歌曲集Cantica Aviditatisより「冬の時代に」のモティーフであり、コミタスの冷え切った心を表現している。トルコの民族楽器ズルナの音色を模したオーボエによって奏でられるトルコの民謡Ben Bu Yıl Yarimden Ayrı Düşeliはオスマン帝国を表す主題として用いられる。さらにダブルリード楽器によってコミタスが作曲したミサ曲より〈主よ憐み給え〉が祈りの主題として奏でられ、トランペットによって平和の主題としてコミタスが作曲した〈やまうずら〉の断片が現れる。
8分の6拍子の提示部では、春の情景を歌うコミタスの歌曲〈犂と鳩〉による第一主題が現れる。テナーサックスのソロが奏でるコミタスのピアノ曲『6つのダンス』よりMalaliとUnabiの動機によって優雅な動きがもたらされる。穏やかな雰囲気は一転し、嵐のような展開部に突入する。〈私は燃えている〉の主題がフガートで畳みかけられ、1915年のアルメニア人虐殺の前触れとなるそれ以前のいくつかの虐殺の記憶がよみがえる。嵐が去った後には断片的な記憶がいくつもコミタスの頭をよぎる。祈りの主題を経て再現部に入るが、提示部ほどの穏やかさは影を潜め、これから起こる出来事を予感させるように変ロ短調の和音で終わる。
第二楽章 「1915年4月」 Allegro ヘ短調
“barbaro”「野蛮に」という発想標語が与えられたスケルツォ。ショスタコーヴィチの交響曲第十番を彷彿とさせるような一気呵成のアレグロが展開される。第一楽章で登場したBen Bu Yıl Yarimden Ayrı DüşeliとSüpürgesi Yoncadanという二つのトルコ民謡が複雑に絡み合いながら、オスマン帝国による暴力のすさまじさが表現される。トルコの主題に重なる「私は燃えている」や「主よ憐み給え」の主題は、突如として理不尽な暴力にさらされたアルメニア人の戸惑いや苦痛を表現している。
第三楽章 「嘆き」 Adagio 変ホ短調
最高潮に達した暴力と混乱は突如として打ち切られ、イングリッシュ・ホルンが祈りの主題〈主よ憐み給え〉を奏でる。失った故郷を嘆くコミタスの民謡〈鶴〉の主題がオーボエによって悲痛に奏でられる。抑えきれない心の内の叫びがtuttiの〈主よ憐み給え〉として爆発する。
第四楽章 「永遠なる平和」 Allegretto 変ホ長調ー変ロ長調
ロンドソナタ形式。3+2、2+3の複合変拍子に乗って第一楽章の提示部のリズムが再現される。コミタスのピアノ曲『6つのダンス』よりHet u arachの主題が牧歌的に奏でられ、デ・ブールの〈永遠の命〉の主題が平和で幻想的な雰囲気を醸し出す。起こりえたかもしれない平和な未来を夢想しながら、アルメニアの子どものためにコミタスが作曲した童謡〈やまうずら〉の主題が奏でられる。平和な夢の中にアルメニアの民謡とトルコの民謡がともに溶けていき、変ロ長調の和音で両者の調和を象徴するかのように終わる。変ロ短調で始まった楽曲は変ロ長調で幕を下ろすが、これは決して解決ではない。過去に起こった虐殺が現在で解決することはないが、未来を生きるアルメニア人とトルコ人は調和の下に平和に共存していけるかもしれない。そんな願いをコミタス(=デ・ブール)は込めている。
商業主義にまみれた現代の吹奏楽では、悲惨な出来事や平和をテーマにした標題音楽が濫造されている。作曲家が糊口をしのぐための飯の種の一つでしかないこれらの楽曲は、アマチュア演奏家のエンターテインメントのために消費され、そこではかろうじて持っていたテーマ性も矮小化され擦り切れる寸前である。しかし、デ・ブールの「コミタスに捧ぐ」は違う。この楽曲を貫く苦しみは、コミタスやアルメニア人が体験した苦しみであるとともに、その経験を音楽で表現しようとしたデ・ブール自身の苦しみでもある。虐殺により犠牲となった100万人以上の無辜の民の命、敬愛するコミタスの命に真正面から向き合い、デ・ブールは苦しみながら音を紡いだ。そしてこの辛い記憶の追体験があるからこそ、〈やまうずら〉の旋律に込められたコミタスの、そしてデ・ブールの平和な未来への祈りは説得力を持つのである。さらにデ・ブールはこの主題を精密な筆致で古典派の交響曲というクラシック音楽の保守本流に落とし込む。この作曲家人生を賭けた大墓標を、自分事として向き合い平和への祈りを共有するのか、それともただのエンターテインメントとして消費するのか。演奏する側と聴く側は試されている。
関連リンク
アルメニアン・コラム(全5回) 原曲プレイリスト(YouTube)