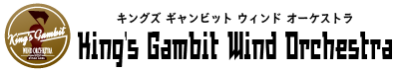第11回定期演奏会 曲紹介
第1部
いにしえの時から / ヤン・ヴァンデルロースト
ヤン・ヴァンデルロースト作曲『いにしえの時から (英訳:From Ancient Times)』は、ヨーロピアン・ブラス・バンド・アソシエーション (EBBA)のコンクール課題曲として書かれ、2010年に吹奏楽版が日本で初演された。
2つ以上の旋律を同時に重ねる多声音楽に“ポリフォニー”と呼ばれる形式が多用されるこの曲は15世紀から16世紀のルネサンス期にポリフォニーを駆使して黄金時代を迎えた“フランドル楽派 (フランダース・ポリフォニスト)”と呼ばれるベルギーの作曲家たちの音楽にインスパイアされた作品である。
曲は鍵盤楽器による不規則なリズムで始まり、やがて1本の旋律とそれのエコーの旋律をユーフォニアムが奏でて主題が提示される。霧が晴れる前のような、楽派としての形式が確立される前のつぼみのような不安と期待の混じった音楽が続く。
ポリフォニーの技法を現代の吹奏楽音楽に昇華させた結果、同時進行する動きは、曲の始めに近いところで現れるサクソフォン・セクションやトロンボーン・セクション等の各アンサンブルだけでなく、木管、金管、打楽器の別なく奏でられる。
その後、ティンパニのソロに導かれて曲は徐々に速度を上げ打楽器アンサンブル、トロンボーンの強烈なグリッサンドを経て、楽譜上で“Estampie”と記された部分に入る。エスタンピーとは中世ヨーロッパのダンス、楽式を指しており、楽器群の組み合わせや速度を変化させながら、手加減のない超絶技巧満載の場面が次々に現れる。
中間部はフリューゲルホルンに始まり、トランペット、サクソフォン、クラリネット、ホルン、フルート、と管楽器のソロが続いていく。
その後、楽譜上で“Hommage a Adolphe Sax”と書かれた場面になる。この後半部分には、ベルギー出身のサクソフォンやサクソルンの発明者アドルフ・サックスへの敬意が込められたシーンでありコーダに至る前に現れる心が温まるような美しいメロディーとハーモニーが聴かれる箇所が特徴的である。この部分で重要な役割を担うユーフォニアムによって歌われるオマージュの旋律は徐々に盛り上がり、クライマックスを迎えた後はサクソフォン・アンサンブルが再び旋律を奏で、アドルフ・サックスへ捧ぐ楽章は締め括られる。
やがて、バンド全体の合奏による激しい連符、クレッシェンドを経て“Con grandezza! (おおらかに、壮大に)”と楽譜に書かれたフィナーレに至る。各セクションがカノンのように重なり合いながら主題を壮大に歌い上げ”Presto”へと続く。曲は一転スピードを上げ、息つく間もなく幕を閉じる。
“いにしえの時から”進化する音楽を21世紀までの様々な要素に触れながら振り返る、走馬灯のような一曲となっている。
(文責:大泉春絵)
オクトーバー / エリック・ウィテカー
エリック・ウィテカー(1970~)はアメリカの作曲家、指揮者である。学生時代には合唱曲の作曲を専門として学んでおり、現在は合唱のほかに、吹奏楽や弦楽の分野でも作曲、指揮活動を行っている。彼の作品はしばしば「無重力的」と評される。ふわふわとしたつかみどころのない音の数々が、静かに大きな雲のように形を成していき、いつの間にか姿を消してしまう。今回演奏する『October』(2000)でもそのイメージを確認することができる。
『October』は、ネブラスカ州の高校生バンドの共同委託により作曲された。技術的にごく易しい曲にするようにとの依頼があり、エリックは、『率直に言って、「簡単」な音楽を書くことは、私がこれまでにやってきた中で一番難しいことの一つです。』とコメントしている。たしかに、今回の演奏会で取り上げるプログラムの中では、際立って「易しい」。しかし、素朴なフレーズが静かに積み重なったり、発散したりしながら大きな音楽を成していく『October』には、エリックの作品らしいゆったりとした温かさや優しさを十分に感じることができる。この雰囲気は、むしろこの曲の「易しさ」により増強されているのかもしれない。ぜひ、エリックのこうした世界観を楽しんでいただきたい。
エリックはほかにも『ラスベガスを喰い尽くすゴジラ』(1996)など、映画音楽に準ずるようなユーモラスな作品も複数手掛けている。彼の作品は世界中で高く評価されており、イギリスで毎年8週間に及んで開催される、BBCプロムスという大クラシックコンサートで彼の作品が演奏されるなど、海外での活躍ぶりはかなりのものである。それに反し、日本の吹奏楽界ではなかなか彼の名が浸透していないようである。コンクール主義的な文化が蔓延する日本の吹奏楽界隈からは、彼の「優しい」音楽が単なる「弱い」音楽として見過ごされてきたのかもしれない。彼の作品にしばしば登場する、手拍子、歌声、叫び声などのエリックらしいユーモラスな表現が、多くのコンクールで禁止 (拒否) されていることも関係しているだろう。
当団の『October』が、エリックの「優しい」音楽との出会いの場になることを願ってやまない。
(文責:宮本琉伊)
「私は心休まらない」による交響的変奏曲 / ハルディ・メルテンス
本作品の原題「Variazioni Sinfoniche su “Non Potho Reposare”」は、日本語では「“私は心休まらない”による交響的変奏曲」と訳される。この”Non Potho Reposare (私は心休まらない)”とはイタリアのサルデーニャ島に伝わる歌であり、文献によっては”No Potho Reposare”とも表記される。その歌詞は1915年にサルヴァトーレ・シーニによって書かれた”A Diosa (女神へ)”という最愛の女性へ向けた思いをつづった詩を基に構成されている。サルヴァトーレ・シーニはサルデーニャ島出身の法律家で、詩人及び作家としても活躍した。1920年にジュゼッペ・レイチェルによってこの詩にのせた三拍子の旋律が作られ、今日に伝わる”Non Potho Reposare”の原型となった。インターネット上を探せば、サルデーニャ島出身の歌手を中心に数多くの人々によって歌われている”Non Potho Reposare”を視聴することができる。
サルデーニャ島はシチリア島に次いで地中海で二番目に大きな島で、四国より一回りほど大きな面積を有する。先史時代から人々が定住し、古くから牧羊が盛んに行われていたとされている。今日ではイタリアの一部であるが、サルデーニャ独自の言語を持つなど、文化的にも独自性の強い土地柄である。地中海のほぼ中央に位置するため、古来より交通の要衝・貿易の拠点として栄え、古代ギリシャ以前の文明との交流が記された遺跡や商人によって築かれた市街や砦など、数々の歴史的建造物が残されている。一方でその地理的な要因から、フェニキア、カルタゴ、ローマ帝国、アラゴン王国などの影響下に置かれた歴史も併せ持つ。その歴史的な影響は今でも色濃く残っており、サルデーニャ北部の町では高齢の方を中心にスペイン北東部の言葉であるカタルーニャ語が通じると言われている。また、サルデーニャ島は近代イタリア建国にも深く関わっている。1720年にサヴォイア家がサルデーニャ島を領有してサルデーニャ王国が建国された。サルデーニャ王国はヴィットーリオ・エマヌエーレ2世の時代に北部イタリアを統一し、南部を征服したガリバルディ率いる勢力と合流して1861年のイタリア王国建国の礎となった。

第二次世界大戦後、工業化によって経済的な復興を成し遂げたイタリア北部に対して、農業が主産業であったサルデーニャ島を含むイタリア南部は貧困が進んでいた。そのような状況下で、サルデーニャ人の中には海外へ出稼ぎに出るものも多くいたという。
このような長い歴史的背景の中で、サルデーニャ人には”The Sardinian Sickness (サルデーニャ病)”とも呼ばれる強い帰属意識が養われていった。愛する女性への歌であった”Non Potho Reposare”はサルデーニャに対する郷愁をあらわす歌へと変化していき、サルデーニャ人の帰属意識の象徴ともいうべき歌となったのである。
本楽曲の編成上の特徴として、バスサックスとチェロの存在がある。バスサックスの存在感は楽曲序盤のサックスアンサンブルにて最も感じることができるだろう。日本でバスサックスが編成に加わる楽曲が演奏される機会はあまり多くない。その編成上の効果をぜひ味わっていただきたい。口惜しくも本演奏会ではチェロを編成に加えることができなかったが、本楽曲の主題である”Non Potho Reposare”をユーフォニアムがチェロパートに代わって歌い上げる箇所は必聴である。
最後に”Non Potho Reposare”の歌詞の一例を付記しておく。前述の通りこの歌は様々な歌手によって歌われており、それぞれ歌詞に微妙な差異があるのだが、ここではサルデーニャ出身の歌手であるAndrea Parodi の歌う”No Potho Reposare” の歌詞の全文とその英訳、本紹介文筆者による簡単な和訳も添えておく。
| 【No Potho Reposare】
No potho reposare, amore ‘e coro, Si m’esseret possibile d’anghelu, No potho biver, no, chena amargura T’assicuro chi a tie solu bramo |
【I Cannot Rest】
I can’t rest, love of my heart, If it were possible, I would take the shape For you a beautiful world I can’t live without bitterness, I assure you that I only desire you, |
【私は心休まらない】
私は心休まらない、心から愛している、いつだってあなたのことを思っている。 もしできることなら、私は天使の姿や目に見えない精霊の姿となって、この空から太陽や星々を盗み、あなたのために美しい世界を作り、あらゆる吉事をあなたに授けるだろう。 私は苦しみなしには生きていけない、親愛なるあなたが傍にいなければ。 約束しよう、私はただあなただけを望んでいる、とても愛している、愛している、愛している。 私は苦しみなしには生きていけない、親愛なるあなたが傍にいなければ。 約束しよう、私はただあなただけを望んでいる、とても愛している、愛している、愛している。 |
英訳:LyricsTranslate.com より引用。Translated by Hampsicora
https://lyricstranslate.com/en/translator/hampsicora
(文責:滝澤大希)
第2部
トリトン / 長生淳
本作は2010年に東邦音楽大学の創立70周年記念委嘱作品として書かれた作品である。同大学が属する学校法人三室戸学園にちなみ、「三」楽章構成、「三」全音の動機を使い、「三室戸」を読み変えて導き出した、ミーシードという音形を主題に循環主題的に用いるといった趣向を盛り込んでいる。
曲名のトリトンはギリシャ神話に登場する海神「トリトン」と、動機として用いられている全音三つ分に当たる音程「三全音 (英語でtoritone)」がかけられている。「トリトン」は半人半魚の海神で、同じく海神であるポセイドンの息子である。海神トリトンは、不思議な力をもつ法螺貝を用いて海流を変えたり、波を立てたり鎮めたりすることができる。この曲では海が見せる荒々しさや穏やかさと言った多面的な表情を現代社会になぞらえて表現し、それに立ち向かい旅立っていく学生の様子が三楽章にわたって描かれている。
第一楽章
全曲の中でも特に海のイメージを強く持って作曲された楽章である。海の激しく荒々しい一面を描いており、若者たちが立ち向かっていく社会の荒波を重ねている。
海神トリトンの吹く法螺貝をイメージしたホルンとトロンボーンによる緊張感のあるファンファーレで曲の幕が開ける。このファンファーレの旋律は三全音の動機から始まり、1楽章の中で形を変え何度も現れる大切な主題である。雄大な流れる波のような旋律が楽器の数を増して現れた後、一転して荒れ狂う波を表現する快速部分に突入する。4分の4拍子と4分の3拍子の変動を繰り返し、複雑なリズムと様々な音色が入り混じることで、海の様々な表情が表現される。最後まで勢いが衰えることなくダイナミックに楽章を終える。
第二楽章
前楽章と対照的に穏やかな海を感じさせる楽章である。母なる海と、落ち着いた学園の中、 そして学んでいる学生の音楽に携わる喜び、ふとよぎる不安や孤独といった内面が重ねられている。
波紋を思わせるような静かな下降系のベルトーンから始まり、揺れるような美しい旋律が続く。叙情的なクラリネットのソロのある中間部から、舞台上のコルネットと遠くから聞こえるトランペットによる三連符の掛け合いを経て、雄大で包み込むような旋律へと発展していく。冒頭のベルトーンが再現された後、新たな展開の予感とともに楽章を閉じる。
第三楽章
これまでの楽章を受けて、「学校から荒波の中の航海へ旅だっていく若者達を応援し、学んだ音楽の力で少しでも荒波を鎮めてもらいたい」という願いをこめて作曲された楽章である。
スピード感のある8分の12拍子で進行する。少人数で波のような主題が提示され、次第にさまざまな楽器によって変奏されながら拡大していく。徐々に「うねり」が厚みを増し、一つの大きな波を作ったのち、トランペットによるファンファーレが高らかに歌われる。中間部で前楽章の旋律が再現され、学園で学んだ音楽の力を生かし社会に立ち向かってほしいという作曲者の願いが表現されている。少しテンポが落ち着いたのち、力強く朗々と歌われる旋律とともに曲はクライマックスを迎える。
本日、第2部ではトリトンに続いて長生氏の交響曲第5番「餞の時鐘」を演奏する。どちらも困難に立ち向かう若者への応援歌として作曲されている。2曲の類似点や相違点を感じながらお聞きいただきたい。本日の演奏が皆様にとっての「応援歌」となれば幸いである。
(文責:相川諒介)
交響曲第5番「餞の時鐘」/ 長生淳
作曲家・長生淳は1964年茨城県生まれ。3歳でピアノを、7歳でヴァイオリンを始め、東京藝術大学音楽学部作曲科および同大学院修了。永富正之、野田暉行に師事し、第2回日仏現代音楽作曲コンクール特別賞、第54回日本音楽コンクール作曲部門第2位 (1位なし)、2000年度武満徹作曲賞など、数々の受賞歴を持つ。吹奏楽、管弦楽、室内楽、映像音楽と幅広く活動し、5つの交響曲をはじめ『トリトン』『波の穂』『翠風の光』など、多くの作品を世に送り出している。
『交響曲第5番「餞の時鐘」』は、大阪大学吹奏楽団の委嘱により作曲された。当初は2020年12月の第50回定期演奏会で初演予定であったが、コロナ禍での公演中止により、委嘱を行った当時の団員による演奏は実現しなかった。その一年後、2021年12月に久保田善則の指揮により同大で初演された。副題の「餞の時鐘」および英題は、中止後の団内公募で決定されたもので、印象的な楽器や作曲者の思いに着想を得て命名された。
本作は4楽章構成で、個人や集団が「目標を模索し、挑戦し、困難を乗り越えて成長していく」物語を描いている。人生に迷いながらも歩み続け、壁にぶつかっても諦めず、最後にはさらなる高みへと進んでいく姿を表現した豊かな旋律と展開には、「聴く者に寄り添いたい」という作曲者の願いが込められており、逆境に立ち向かう人々の心を励ます力を持った作品といえる。
第1楽章では「夢や目標が形になっていく過程」が描かれる。冒頭はアルトクラリネットによって静かに幕が開かれる。その後すぐ、打楽器による上昇音型が現れるが、この上昇するような動きは「夢に近づく力」を象徴しており、全曲を通じて様々な形で現れる。散り散りだった音が1つの線のように繋がっていき、力強い旋律へと成長していく。その過程で困難を象徴する転調やテンポ変化が挟まれるが、再び音楽は高みへと向かい壮大なクライマックスを築く。終盤では、曲全体を通して鍵となる動機が繰り返され、静かに幕を閉じる。
第2楽章では「前向きな挑戦と喜び」が描かれる。明るい調性と活発なテンポで始まり、喜びに満ちた旋律が高らかに奏でられる。【木管楽器による軽やかな音型】と【金管楽器による1楽章終盤の動機に基づいた音型】の2つのモチーフが対比され、それぞれが繰り返されることで高揚感が演出されている。浮遊感のある拍子と祝福のように響く鐘の後には、困難が再び立ちはだかることを思わせる暗い調性へと転じる。しかし最後は希望の調べが戻り、喜びがバンド全体によって再び歌い上げられ、力強く締め括られる。
第3楽章では「喪失感や痛みから、再び希望を見出す過程」が描かれる。初演される予定だった演奏会が中止になったことを受け、作曲者の意向で当初の予定より演奏会ができない「喪失感・痛み」がより深く盛り込まれた。哀愁を帯びたファゴットとアルトクラリネットの旋律を皮切りに、悲しみが各楽器へ伝播し、抑えきれない感情が音に込められる。夢が遠く感じられる切ない表現や、苦悩の中に微かな希望を見出そうとする様子が、テンポの緩急や音色の変化を通じて表され、最後は未来への希望を予感させる上昇音型で終わる。
第4楽章では「過去を超えた更なる高みへの挑戦」が描かれる。冒頭では1楽章の上昇音型がより力強く明確に展開され、その後これまでの動機や旋律が随所に回帰することで、経験を糧に進化していく様子が描かれる。複雑な拍子が未曾有の困難を表すが、それに抗い乗り越える姿が、反復される旋律や変化に富むリズムで表現される。絶望の底から希望を手繰り寄せるように、苦しみと努力が重なり合うような音楽展開が続き、最後は圧倒的な響きで目標達成の喜びを描きつつも、さらなる夢へと駆け抜けて壮大に締め括られる。
(文責:瀧康二)