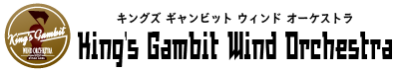第11回ユアコンサート 曲紹介
第1部
祝典序曲 / D.ショスタコーヴィチ
本日の演奏会の幕開けを飾るのは、ドミトリー・ショスタコーヴィチ作曲の《祝典序曲》です。原曲は1954年、ロシア革命37周年記念して作曲されたもので、祝祭的な華やかさと躍動感あふれる音楽が特徴です。冒頭から鳴り響くファンファーレ、軽快なリズム、そして高揚感あふれるフィナーレへと続く構成は、まさに「祝典」の名にふさわしい壮大な作品です。
今回演奏するのは、ハンスバーガーによる吹奏楽編曲版。オーケストラ原曲の迫力をそのままに、吹奏楽ならではの鮮やかなサウンドが加わり、よりエネルギッシュな魅力が引き立っています。冒頭の一音から、まるで祝祭の門が開かれるような高揚感があり、聴く人の心を一気に演奏会への世界へと引き込んでくれます。ステージと客席が一体となり、今日という特別な時間が動き出す瞬間を、ぜひ一緒にお楽しみください。
(文責・指揮:池田恭祐、スペシャルサンクス:ChatGPT GPT-4o)
「風の谷のナウシカ」ハイライト / 久石譲 / 編曲:真島俊夫
《「風の谷のナウシカ」ハイライト》は5曲で構成されるメドレーです。映画「風の谷のナウシカ」の世界観を楽しむだけでなく、吹奏楽編成だからこその各パートのソロにもご注目ください。本作品に収録されている各曲が使用される場面描写を以下に解説します。
◆「風の谷のナウシカ」~オープニング~
「火の七日間」と呼ばれる戦争が巨大産業文明を灰燼に帰してから1000年後、錆とセラミック片に覆われた荒れた大地に腐海と呼ばれる有毒の瘴気を発する菌類の森が広がり、衰退した人間の生存を脅かしていた。この曲は、人間が住む土地が限られ、王蟲をはじめとする巨大な蟲たちが闊歩する崩壊後の世界観が表現されています。
◆クシャナの侵略
ある夜、腐海のほとりにある風の谷に巨大な輸送機が墜落した。そこに積まれていたのは、「火の七日間」で用いられた旧世界の生物兵器である巨神兵だった。この曲は巨神兵を狙い、侵略してきた異国の皇女・クシャナが率いるトルメキア軍と風の谷の対立、そして高まる緊張感が表現されています。
◆メーヴェとコルベットの戦い
トルメキアと敵対するペジテが王蟲を利用し、風の谷を襲わせる計画を知ったナウシカは、急いで風の谷に向かうためその場を離れようとするも、ペジテの航空機に捕らえられてしまう。船内にいた良識ある人に助けられ、ナウシカの愛用する飛行装置・メーヴェに乗って脱出するが、トルメキアの航空機・コルベットに襲撃されてしまう。手数の多さを駆使して追撃するコルベットと、小回りの利く機体を持ち、軽やかな動きで攻撃をかわすメーヴェの疾走感や緊迫感が表現されています。
◆ナウシカ・レクイエム
風の谷に戻ったナウシカは、王蟲の群れを誘導するために傷つけられた王蟲の幼生を風の谷の近くで発見し、救出する。しかし、怒りに我を忘れた王蟲の群れは、王蟲の幼生ではなく風の谷へと向かってしまう。ナウシカは王蟲の幼生とともに王蟲の群れの前に降り立つが、群れの動きは止まらずナウシカは跳ね飛ばされてしまう。ナウシカの犠牲によって群れの暴走は止まり、王蟲の力によってナウシカは蘇った。
◆「鳥の人」~エンディング~
蘇ったナウシカは王蟲の触手作り出す金色の草原を歩く。それは「その者、青き衣をまといて、金色の野に降り立つべし。」という風の谷の古き言い伝えを体現していた。ナウシカは風の谷に、王蟲は腐海へ帰り、風の谷には平穏な生活が戻ってきた。この曲では、明るいとは言えない「ナウシカ」の世界でも、確かに希望が芽生えているということが表現されています。
(文責:佐々木蒼依)
交響詩《モンタニャールの詩》 / J.ヴァンデルロースト
ヨーロッパの作曲家ヤン・ヴァンデルローストは、吹奏楽のために数多くの名作を生み出してきた現代を代表する作曲家の一人です。《アルセナール》《プスタ》《カンタベリー・コラール》など、世界中の吹奏楽団で親しまれる彼の作品は多岐にわたります。その中で《モンタニャールの詩》は、イタリア北部アオスタ地方の自然と文化を音楽的に描き出した大規模な交響詩であり、ヴァンデルローストの叙情性と構築力が凝縮された一曲です。
モンタニャールとはフランス語で「山岳地方の人々」を意味します。アルプスに囲まれたアオスタ渓谷は、古くから自然と共に生きる人々の営みが育まれてきた土地です。ヴァンデルローストはその風土を音楽に写し取り、壮大な山岳風景や素朴な民衆の生活、そしてそこに息づく歴史や精神性を吹奏楽の響きで表現しました。
冒頭は静かなコラール風の導入部から始まり、アルプスの夜明けを思わせる透明感ある響きが広がります。やがて木管が奏でる民謡風の旋律が姿を現し、のどかな山村の情景を描きます。戦いの場面をあらわす荒々しい音楽を挟みながらも、中間部ではテンポが速まり舞曲的なリズムが展開し、祭りや人々の活気を思わせる場面が生まれます。一方で金管による力強いファンファーレは、雄大な山岳の威厳や厳しい自然を想起させ、音楽は劇的な表情の変化を繰り返します。終盤では再び旋律が回帰し、積み重ねられたエネルギーが壮麗なクライマックスを築き上げ曲を閉じます。
《モンタニャールの詩》は、単なる風景描写にとどまらず、自然と人間の共生、歴史と文化の厚みを音楽で語りかける作品です。ヴァンデルローストならではの明快な旋律と豊かなオーケストレーションは、立体的な音楽を創り出しており、まるでアオスタの壮大な自然が目の前で展開しているような感覚を与えてくれます。
(文責・指揮:大泉晴絵)
第2部
シェイクスピア・ピクチャーズ / N.ヘス
《シェイクスピア・ピクチャーズ」は、ナイジェル・ヘスが英国王立シェイクスピア劇団のために作曲した音楽を、3楽章から成る吹奏楽版の組曲として自身の手で再構成した作品です。曲名の通り各楽章はシェイクスピアの独立した戯曲をモチーフとしており、ヘスの世界観が存分に味わえる1曲となっています。
1. Much Ado About Nothing ~空騒ぎ~
1598年頃に成立した喜劇がモチーフで、【シチリア島の知事の娘ヒーローに恋をするクローディオ】、【その知事の姪ベアトリスと度々口喧嘩を繰り広げているベネディック】、この2組の恋物語を描いています。クローディオの友人:ペドロが、彼らの恋の手助けをと、クローディオになりすましてヒーローに求婚したり、ベアトリスとベネディックが互いを想いあうようになるよう仕組んだりすることから始まります。しかし、ペドロの異母弟:ジョンの策略でヒーローが浮気をしていると勘違いしたクローディオは彼女との破談を宣言。ショックのあまり失神してしまったヒーローを周囲が死んだように扱ったことをきっかけに、怒れるベネディックとクローディオの決闘にまで発展します。しかしジョンの仲間がこの策略を漏らしてしまったことで全てはジョンの陰謀であったことが判明。ヒーローも生きており、二人は晴れて結婚に至り、さらにはベアトリスとベネディックも結ばれます。
曲は疾走感あるイントロから始まり、ホルンの勇ましい雄叫び、木管楽器の流れるようなメロディー、金管楽器のファンファーレと目まぐるしく場面が変わりつつ展開していきます。最後に冒頭部分が再現され、勢いのままに終結します。ホルンの勇ましいメロディーと木管楽器の旋律の対比をお楽しみください。
2. A Winter’s Tale -The Statue ~冬物語 ― 彫像(亡き王妃の像)~
1610年に成立した喜劇・ロマンス劇がモチーフ。シチリア女王:ハーマイオニがボヘミア国王と不倫関係にあると誤解したシチリア王:リオンティーズは、女王を投獄し、獄中で生まれた王女:パーディタを臣下に命じてボヘミア領内へ捨てさせます。しかし神託によってそれは誤解であったことが分かり、リオンティーズは激しく後悔します。その後、パーディタの行方が分からないまま16年が経ち、ボヘミアで羊飼いに拾われて美しく成長したパーディタは、そこで王子と身分違いの恋に落ちます。若い二人がシチリアを訪れたのがきっかけで、パーディタが王女であったことが判明。王と王女の再会と和解を皆が喜び合う中、女王ハーマイオニの彫像が公開されます。その彫像に胸を打たれたリオンティーズが真の愛を示すと、「自然の魔法」により彫像は本物のハーマイオニとなり、親子は奇跡の再会を果たします。
フルート、クラリネット、バスクラリネットが重なり合う美しくも物悲しいソリからこの楽章は始まり、続いてオーボエのソロ、フルートとイングリッシュホルンのソリで嫉妬と誤解が生んだ悲しみを表現する主題が展開していきます。最後は大団円で終わる物語であるが、終始悲哀をはらんだ切ないメロディーが続き、tuttiの後静かに2楽章は終結する。指揮を振っていて最も好きな楽章。一部の木管楽器とホルン、ハープのみで奏でられる、切なさの中に感じられる和音の美しさにご注目ください。
3. Julius Caesar – The Entry to the Senate ~ジュリアス・シーザー ― 元老院への入場~
1599年成立の歴史劇がモチーフ。群衆に熱烈に迎えられながらローマへと凱旋する将軍:ジュリアス・シーザーは、彼のことを良く思わない議員たちに唆された義兄である高潔な武将:ブルータスに暗殺されてしまいます。「お前もか、ブルータス」と言い残して亡くなったシーザーについて、ブルータスが将軍の死の理由を民衆に向けて演説する一方で、シーザーの腹心:アントニーは、これがブルータスによる暗殺であることを感情的に演説し、民衆を扇動します。やがて暴動に発展し、ローマを追われることになったブルータスは、アントニーとの決戦の末、自害します。ブルータスの亡骸を前にしてアントニーが彼の高潔さを讃える言葉を並べ、劇は終結します。
フルート独奏による語りから始まり、スネアドラムのリズムに乗せられて開始するこの楽章は、時折物悲しい木管群のメロディーや不協和音を含みながら徐々に華々しい音楽へと展開します。盛り上がりを迎えたところでパイプオルガンによって再度主題が提示され、低音楽器との混じり合わないベースラインを奏でながら、葛藤に苛まれながらも金管楽器による強烈なファンファーレが響きます。オーボエソロによる哀悼表現を経て再び金管楽器主体のファンファーレが鳴り響き、音楽は劇的に終結します。終盤のファンファーレや、突如として登場するオルガンの存在感とともに、その中で時折登場するレガートの美しい旋律にもご注目ください。3つの戯曲の中で最もハッピーエンドからは遠い物語であるため、登場人物の死と葛藤に思いを馳せながらお楽しみいただければと思います。
(文責:松瀬広太郎)
幻想序曲《ロメオとジュリエット》/ P.チャイコフスキー / 編曲:青山るり
「幻想序曲《ロメオとジュリエット》」は、ロシアの偉大な作曲家チャイコフスキーが生み出した最初の傑作と言われています。この作品は、彼の師であったバラキレフの熱心な勧めにより1869 年に作曲が開始されました。当初チャイコフスキーは作曲に乗り気ではありませんでしたが、バラキレフの真摯な説得とアドバイスを受けて完成に至ります。初演は不評でしたが、二度の改訂を経て、現在演奏される第3稿が1880年に完成しました。
この曲の最大の魅力は、シェイクスピアの悲劇を3 つの印象的な主題で見事に音楽化している点です。まず、荘重なコラール風の序奏は、修道僧ロレンスが悲劇を振り返る場面を表現します。続く激しい第一主題は、モンタギュー家とキャピュレット家の激しい対立を描き、オーケストラが2 つに分かれて互いにぶつかり合います。そして甘美な第二主題では、ロメオとジュリエットの純粋な愛が、イングリッシュホルンとクラリネットによって奏でられます。有名なバルコニーのシーンでは、フルートとオーボエの対話が二人の愛の誓いを美しく表現します。
展開部から再現部にかけては、物語が急展開していく様子が描かれます。ロメオの追放、別れの夜の愛の確認、そして悲劇的な結末へと音楽は激しく展開します。ロメオとジュリエットの死は、それぞれ鋭い一音で表現され、聴く者の心を打ちます。終結部では葬送行進曲が流れ、木管楽器による天国の調べのような美しいコラールが、二人の魂の昇華を暗示します。
ソナタ形式という堅固な構成の中に、ドラマチックな物語と豊かな感情を見事に融合させたこの作品は、チャイコフスキーの才能が開花した記念碑的な傑作です。華やかなオーケストレーションと心を揺さぶる旋律美で、今なお世界中の聴衆を魅了し続けています。
(文責・指揮 岡﨑正悟)
第3部
The Low-Down Brown Get-Down / O.トーマス
オマリ・トーマスによって2020年に発表された本作は、ファンク、R&B、ソウル、ヒップホップ、ブルーなどのアフリカ系アメリカ人の音楽を基盤としており、その特徴が色濃く表れている「リズム」や「ビート」は、16ビートを基本とし、アクセントや裏拍から始まるフレーズが多用されることで、その特色が一層際立っています。
彼の代表的な吹奏楽作品として、《Of Our New Day Begun》、《Come Sunday》、《A Mother of a Revolution!》などが挙げられますが、本作はそれらの中でも特に「グルーヴ感」が際立っている一曲です。タイトルの「Brown」は、「ナンバーワン・ソウル・ブラザー」として知られる世界的ミュージシャン、ジェームズ・ブラウンにちなんで名付けられています。
曲の冒頭は、金管楽器とサックスによる不協和音で始まり、不穏な空気が立ち込めたかと思いきや、すぐに曲調が一転。打楽器とベースラインが生み出すファンクのリズムに乗せて、さまざまなフレーズが重なり合うように展開されていきます。楽しげな雰囲気の中にも、どこか「哀愁」や「暗さ」が感じられるのは、本作がブラック・ミュージックをルーツとしているからに他ならないでしょう。
中間部では、トランペットによるソロが登場し、それにピアノとコンガが呼応する形で応じます。その後は全奏(tutti)となり、冒頭のテーマが再び演奏されます。
そのまま終結へ向かうかと思いきや、突然テンポが速まり、ハイハットと低音楽器による8 分音符のベースラインに乗って、スリリングな音楽が繰り広げられます。(トーマスは《Come Sunday》でも同様のベースラインを低音楽器に課しており、特にチューバ奏者にとっては大きな試練となっていることでしょう。「私はエレキベースじゃない!」という声が聞こえてきそうです。)そうして最後には、変拍子の中でフレーズがリフレインされ、コードをかき鳴らすようにして壮絶に曲が終わります。
トーマスの文章からは、彼が自身のアフリカ系アメリカ人としてのルーツに誇りを持ち、コンサートステージにおいてアフリカ系アメリカ人の伝統音楽の地位向上に精力的に取り組んでいる姿勢を感じ取ることができます。
本作を通じて、そんなO.トーマスの世界観を存分に味わっていただければと思い、最後に、本作のプログラムノートより彼のコメントをご紹介します。
(文責:勝見創太)
Duende 吹奏楽のための4つの前奏曲/ L.セラール・アラルコン
ルイス・セラーノ・アラルコンは、バレンシア地方出身の作曲家で、基本的には独学で作曲を学び、ピアノや室内楽、オーケストラ、吹奏楽のために多岐にわたる作品を生み出しています。現代的なサウンドをクラシックや伝統的な音楽と融合させることに造詣が深い彼の作品は、各国で非常に高い評価を受けており、世界的に注目されている作曲家の一人です。
本作の題であるDuendeとは、フラメンコにおいて、演奏者がごくまれにしか到達できない、感覚が研ぎ澄まされて魔法にかかったような状態や、他と違う類まれなる優美さを持つ人を表す言葉として使われています。言葉の意味を形容するのみならず、スペイン音楽から着想を得た作品であることが示されており、デ・ファリャの交響的な重厚さ、アルベニスの「イベリア」の親しみやすさ、フラメンコギターの魔力、フラメンコの一種であるサクロモンテの祝祭的な幸福感といったエッセンスを感じることができます。本作の主眼は、スペイン音楽、ジャズ、ポピュラーなラテン音楽の融合にあり、伝統的な背景を持ちつつも国際的で現代的なスペイン社会の現在が体現されています。
ソナタ形式に基づき展開される1楽章.Allegro giustoは、E-F-C-Bの音列が主要な動機となっています。徐々に姿をあらわにする動機により呼び起された、3/4 と4/4を交互に繰り返す舞曲風の拍子パターンは、細かな拍子の変化を交えながら興奮感と不安定さを演出します。フルートにより提示される第1主題はすぐさま第2主題に切り替わり、激しい展開部を迎えます。高揚した再現部から劇的なコーダに入るも束の間、序奏の再現がされますが、緩やかに眠りにつくような静けさで幕を閉じます。
エレクトリック・ベースのシンコペーションリズムを発端とする2楽章.Animatoは、フーガ形式にジャズが落とし込まれています。抒情的な対旋律を巻き込みつつ、ソプラノサックスのアドリブソロを交えて展開し最高潮に達したところで、不意に訪れた静けさのなか冒頭のベースと対照的な音域を奏でるピッコロに導かれ、16分音符のトゥッティで鮮烈に締めくくられます。
対して3楽章.Cadenza a piacere; molto sentino – Lento evocativoは、ミニマルな編成で繊細かつ自由度の高い曲となっています。物悲しいピアノのカデンツァに始まり、木管楽器の内省的な旋律が奏でられ、徐々に濃密な響きとなりますが、その響きが溶け去り、イングリッシュホルンによる提示部を思い起こさせるソロも消えて、静寂が戻ります。
4楽章.Tempo de Buleríaは、その題のとおり、速いフラメンコのブレリアにインスパイアされた曲で、祝祭的な響きの中で❶②③❹⑤⑥❼⑧❾⑩⓫⑫、❶②③❹⑤⑥⑦❽⑨❿⑪⓬、❶②③❹⑤⑥⑦❽❾⑩⓫⑫などの典型的なブレリアのアクセントパターンが複合的に用いられています。複雑な手拍子や強奏の下降形により盛り上がりを見せ、土臭さを纏いながら熱狂的なフィナーレへとなだれ込みます。
(文責:川上ひなた)